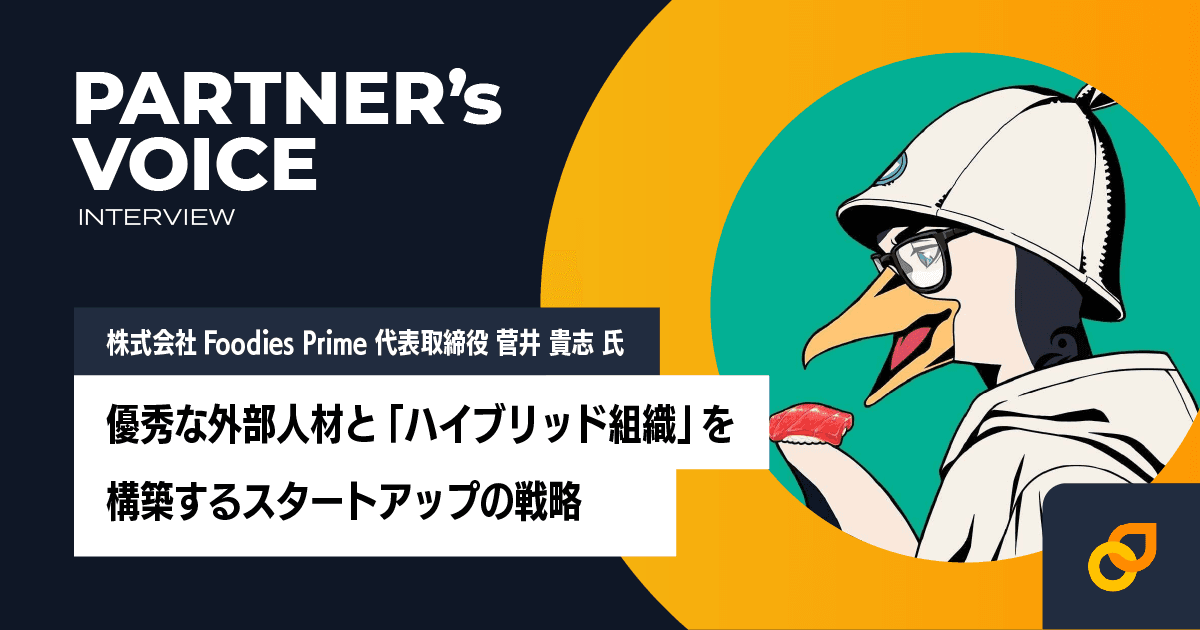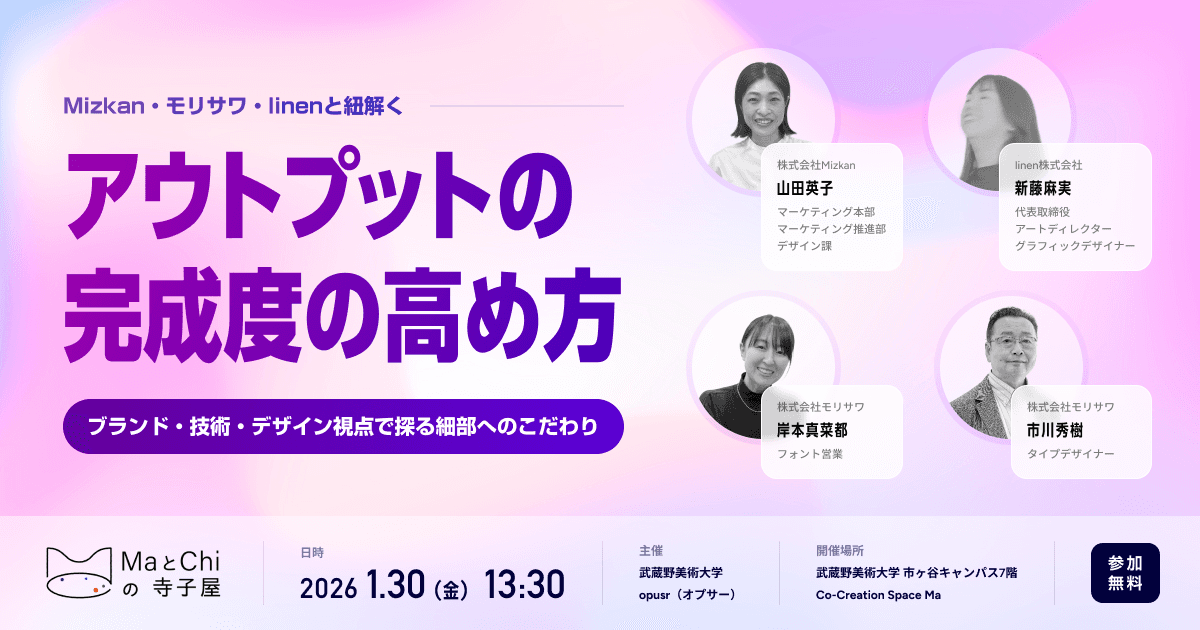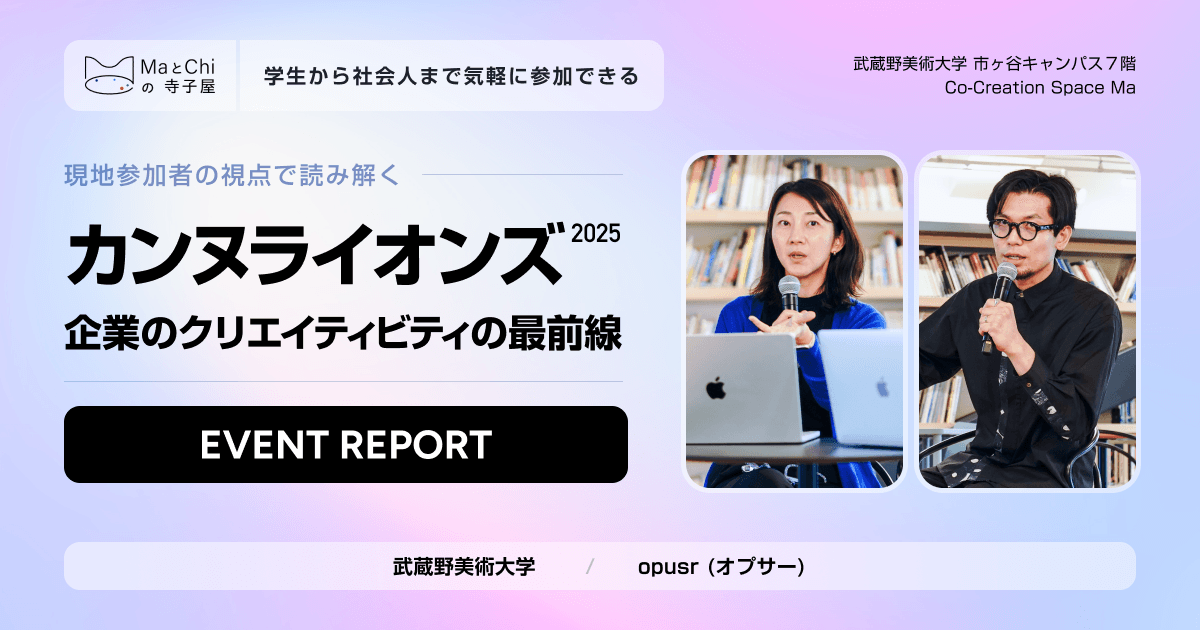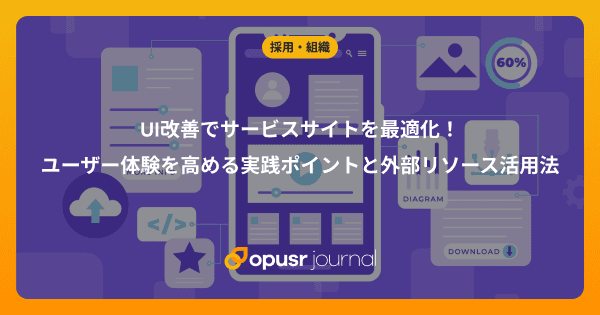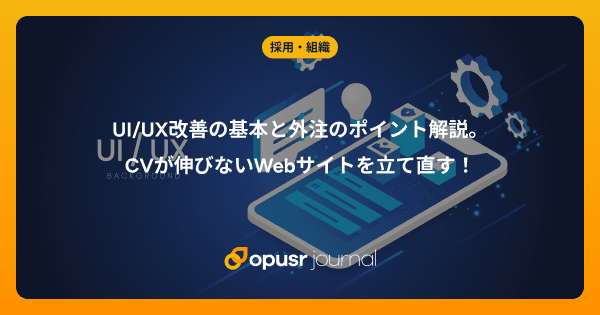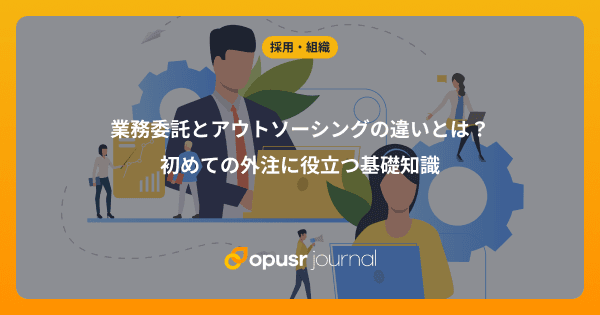溢れ出てくる思いを形にするのがCIデザインである / kern inc. DESIGNER / Art Director タカヤ・オオタ氏
kern inc. DESIGNER / Art Director タカヤ・オオタ氏
業界や分野問わず”デザイン”に関わる方々に、目的や信念、その領域におけるデザインに関する考え方やノウハウを伺っていくコンテンツシリーズ「◯◯のデザイン」。
今回は「企業文化とアイデンティティのデザイン」と題し、企業のアイデンティティをデザイン・設計する意義について、kern inc.のタカヤ・オオタさんにお話を伺いました。

沖縄県生まれ。
立教大学経営学部卒業後、デザイン事務所と事業会社を経て株式会社ケルンを設立。
「企業の思想を意匠に変える。」をテーマに、スタートアップ企業との協業を中心にアイデンティティ・デザインの設計に取り組む。
ロゴは資産価値に対して単価が低かった。アプローチを変えればもっと伸ばせると思った。
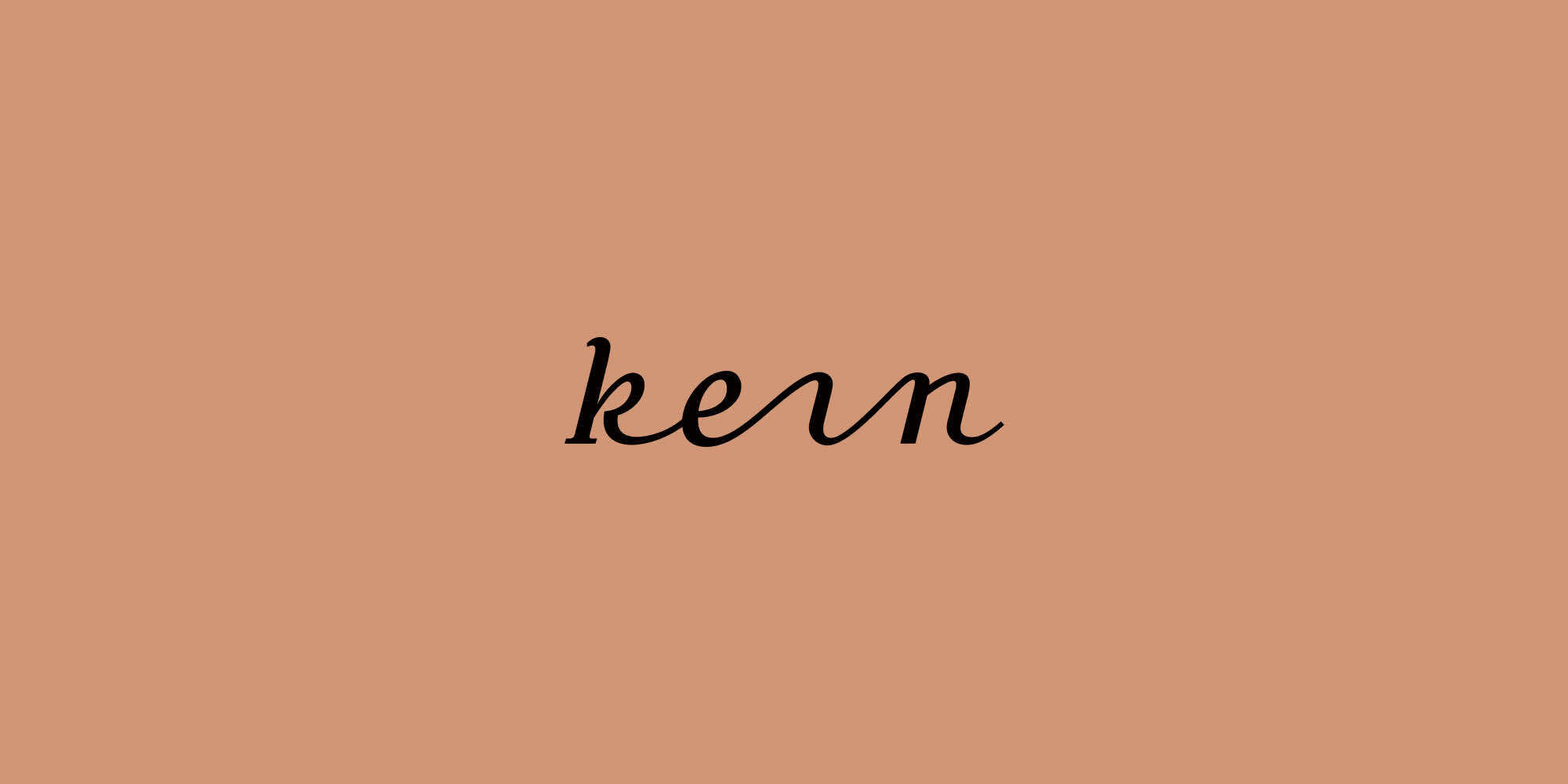
ー早速ですが、現在のキャリアに至るまでについて伺いたいと思います。元々大学で経営学部に進学されたそうですが、そこからデザインの道に進まれたきっかけについて教えてください。
オオタ氏
大学時代、フリーマガジンのサークルに入ったのがデザインを始めたきっかけです。
そのサークルでは志が高い人たちが多く、各々自分の得意分野で活動していく中、自分は得意分野も経験もなかったのでたまたま希望者のいなかったデザインを担当することになりました。
その後、イラストレーターやフォトショップを独学で学び、初めてデザインした冊子がすごく好評で、自分が作ったものを人に見せたり、それに対して驚かれたり喜んでもらうという経験が初めてで、純粋に面白いと感じどっぷり浸かりましたね。
冊子デザインの経験をした後、フリーマガジン以外にもデザインをしていきたいと思って、web上に自身の作品を公開してX(旧Twitter)でデザインをシェアするようになりました。
当時、UIデザイナー以外でX(旧Twitter)を利用して自身のデザインを発信しているグラフィック系のクリエイターが少なかったこともあり、デザイン事務所の方やスタートアップ企業から声をかけていただくようになりました。
ーその後クリエイティブエージェンシーに就職されましたが、CIデザインはその時からやられていたのでしょうか。
オオタ氏
新卒で入社した事務所では広告クリエイティブやwebデザインを主に担当していました。
webとロゴのデザインがセットになっているプロジェクトも多かったのですが、業界全体として当時から意匠デザインの制作費はあまり高くなかったんです。
ロゴは企業や事業の顔として資産価値が高く原価償却期間も長いのに、どうして他の制作物の1/10程度しかお金が頂けないのだろう?と疑問をもっていました。
これは、考え次第で伸びしろがあるなと思ったんです。
そこで、海外のデザインファーム、たとえばペンタグラムのような企業を調べながら、どのように意匠に価値を与えられるのか考えました。単に見た目ではなく企業文化や思想を言語化して、それを意匠に反映していくというアプローチを取ればもっと価値を高められるんじゃないかという考えに至り、CIデザインのアプローチを取り始めたのです。
そんな中、CIデザインとしてしっかり予算を頂いたのは、ベンチャーキャピタル「ANRI」さんとのプロジェクトです、2015年頃のお仕事になります。
代表の佐俣アンリさんにX(旧Twitter)で「何か仕事させてください」って返信したのがきっかけでした(笑)
今でこそ失礼だったなと思うのですが、ANRIさんのCIが様々なスタートアップ企業の目に止まり、お仕事をする大きな第一歩、デザイナーとしての転機になりました。
スタートアップ企業は市場や事業に対する考えが明確で、それを自社のアイデンティティに反映する重要性に理解を示してくれる方がとても多い。
そもそもスタートアップという業界自体が未来へ投資するセグメントですから。
そのように、デザインが事業にインパクトを与えてくれると信じてくれている方々のお陰で、僕自身もアイデンティティ・デザインの重要性を再認識できましたし、今のキャリアに繋がっています。
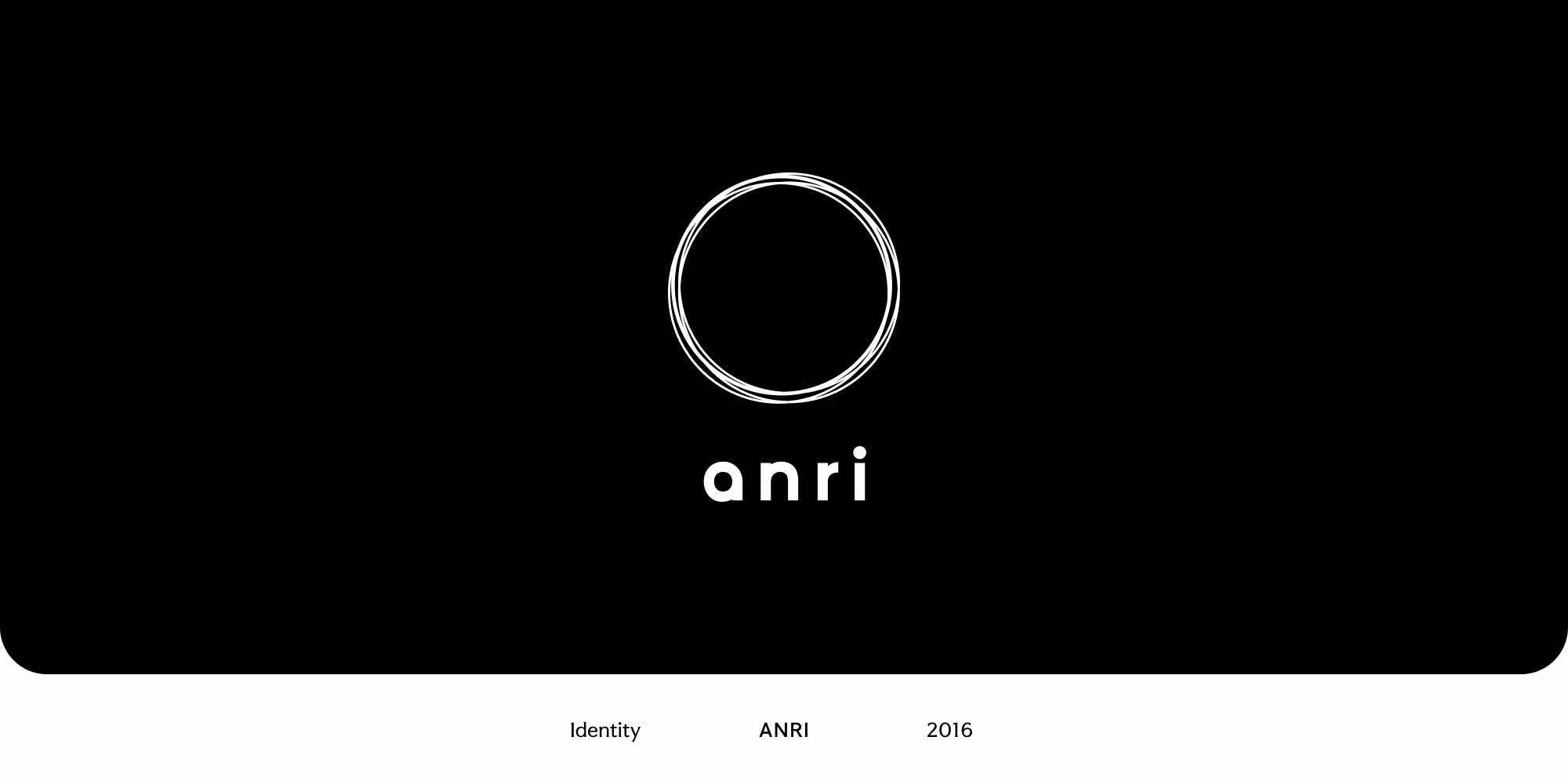
スタートアップは将来的な可変性が高い。だからこそ、未来に残るコアを見つけることが仕事。
ーX(旧Twitter)の1通のリプライからCIデザイナーとしてのキャリアが始まったということですね。
ちなみに、CIとは企業文化や思想を反映するものということですが、実際どのように思想を言語化しデザインに落とし込まれてるのでしょうか。
オオタ氏
私がお仕事をする方の多くは、現行の意匠が持つ課題感と思想を伝達する理想像のギャップを認識しています。
そのため、ディスカッションを通じて重要な要素を抽出し、何をどの程度に表現へ反映させるべきか話し合うことが起点になります。
大枠の方向が決まったら、それらを抽象化してコンセプトに束ねて、複数のデザイン案に落とし込みながら、思想と表現の繋がりを模索していくというのが流れになります。
ただし、実際にデザインに落とし込むフェーズで、伝達したい要素や込めたい意味が多すぎる課題に直面することもあります。
この場合は、事業の方向性が変わっても不変の本質的な要素は何か、つまりメッセージの優先順位づけや掘り下げる作業が不可欠です。
ー伝えたい情報がtoo muchにならないようにリードする必要があるのですね。ちなみにデザインを担当された企業はどこも事業が伸びていると感じますが、タカヤさんから見て何か共通する点はありますか。
他のデザイン領域に比べて事業成長とCIの相関性は低いと考えていますが、総じて事業の思想をアウトプットする重要性を理解している方が多い印象です。
アイデンティティのデザインに精通していなくとも、デザインに投資することが結果的に会社やそこで働く人々へ反映されていくと信じている人とたくさん出会ってきました。
デザインが良いから結果がどうというよりも、その重要性に対して理解のある人たちと仕事をすると、自分も良いものを残せる気がします。
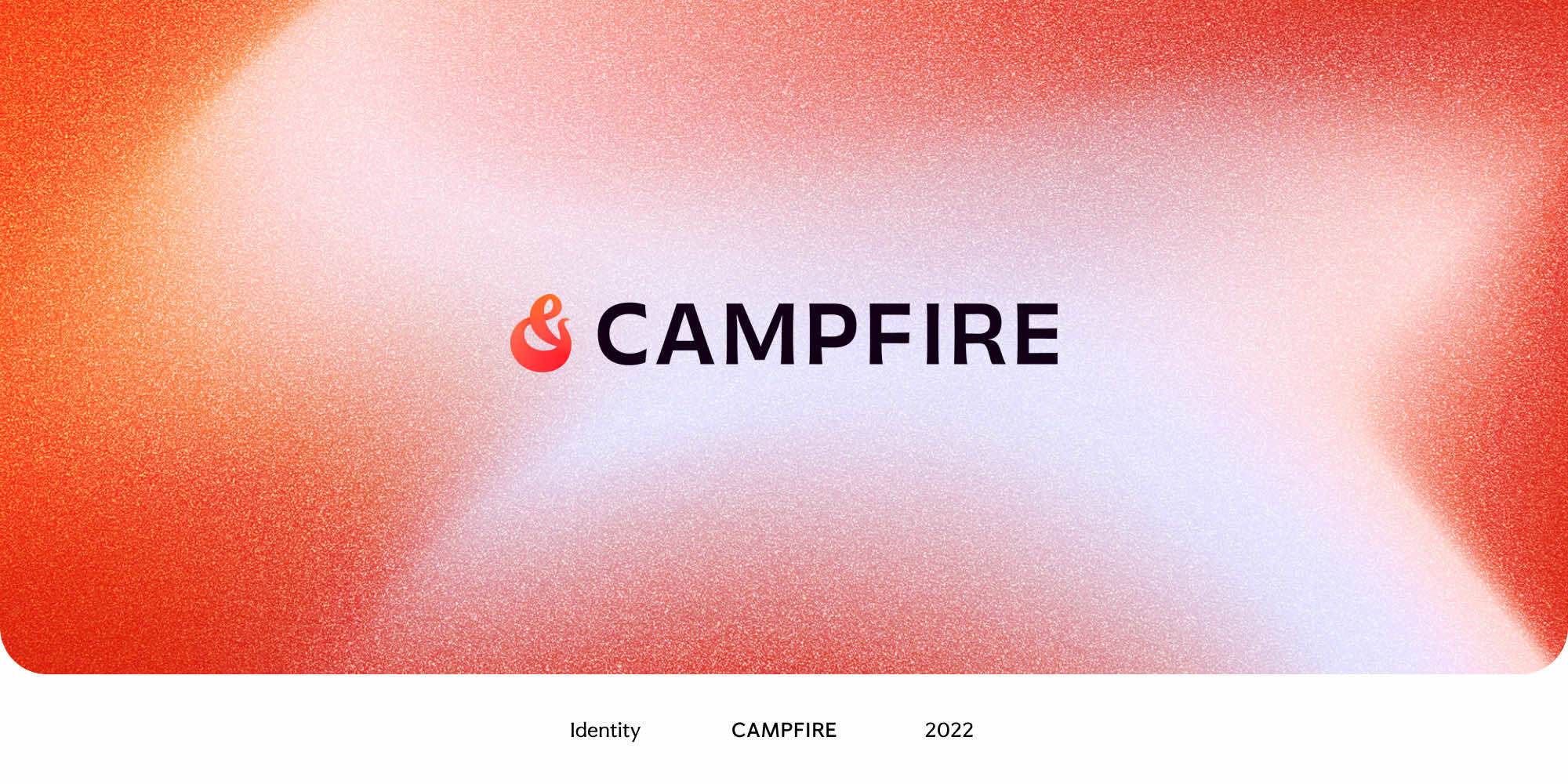
.jpg)
ーなるほど。例えば双方にとって良い結果を生むために、どういう情報をまとめているとより良いデザインが作れると思いますか。
オオタ氏
難しい問いですが、依頼側と受託側の双方が十分に準備できている環境が良いデザインを行うための条件だと考えています。
僕が特に意識しているのは、この2者間に存在する情報の非対称性です。企業側から見れば日々の事業活動の中では当たり前すぎて、言語化されていない事柄がたくさんあります。それを浮かび上がらせていく作業こそがアイデンティティ・デザインの肝ですが、その手前の情報にアクセスしやすいプロジェクトほど双方が手応えを感じることができています。
一方で、そのギャップを埋めるために、社内レクやワークショップをすれば万事解決というわけでもありません。企業の一人一人が当事者意識や思いを持って事業を行っていく中で湧き上がってきた思いを、共にデザインへ込めていきたいですね。
ーありがとうございます。
CIデザイナーとしてのキャリアを切り拓いたきっかけや、CIデザインを行う上で企業側の意識の持ち方について非常に参考になりました。
次回は、現在取り組まれているタイプファウンダリ・プロジェクト「kern typefaces」や今後の取り組みについてお伺いしていきます。
▼後半はこちら
この記事をシェアする



.jpg)



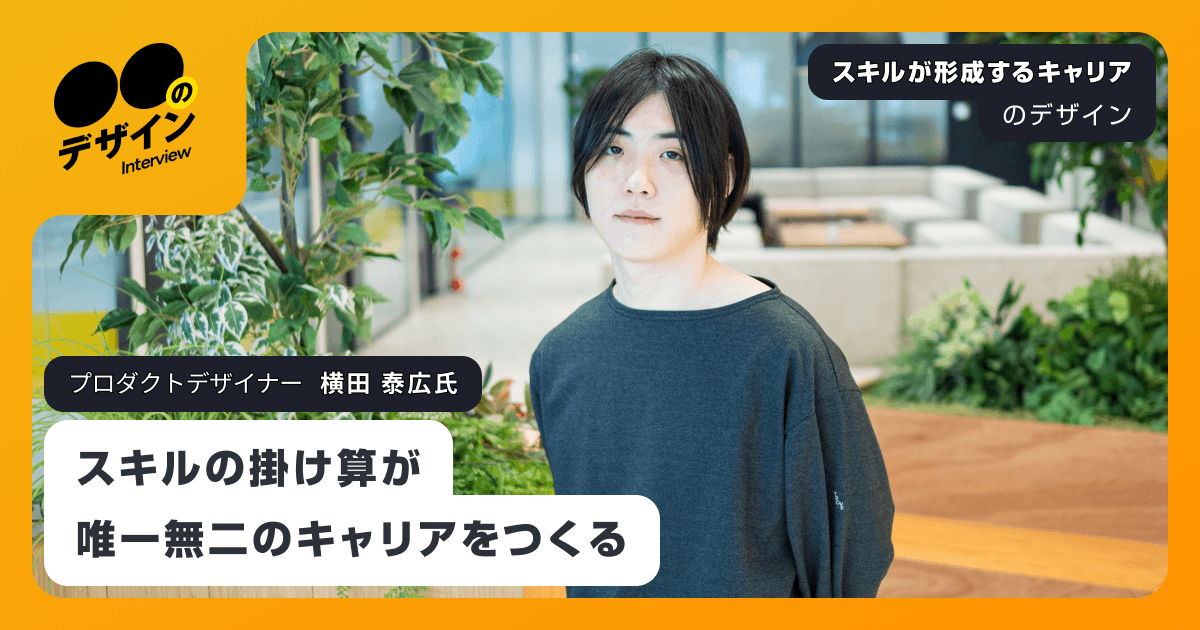
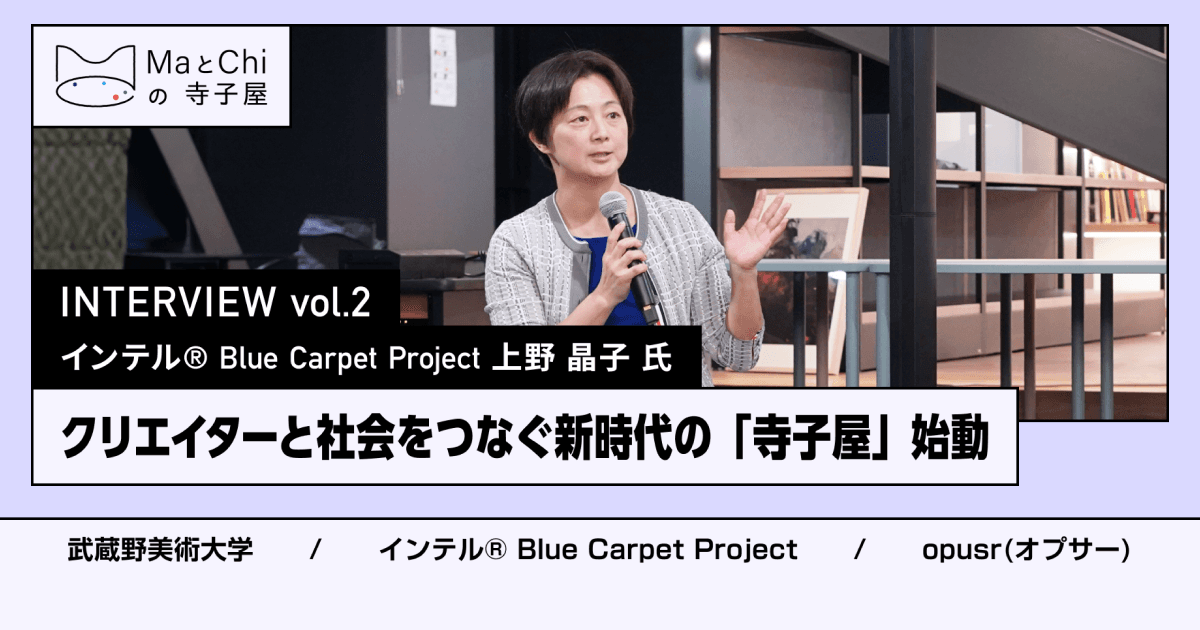
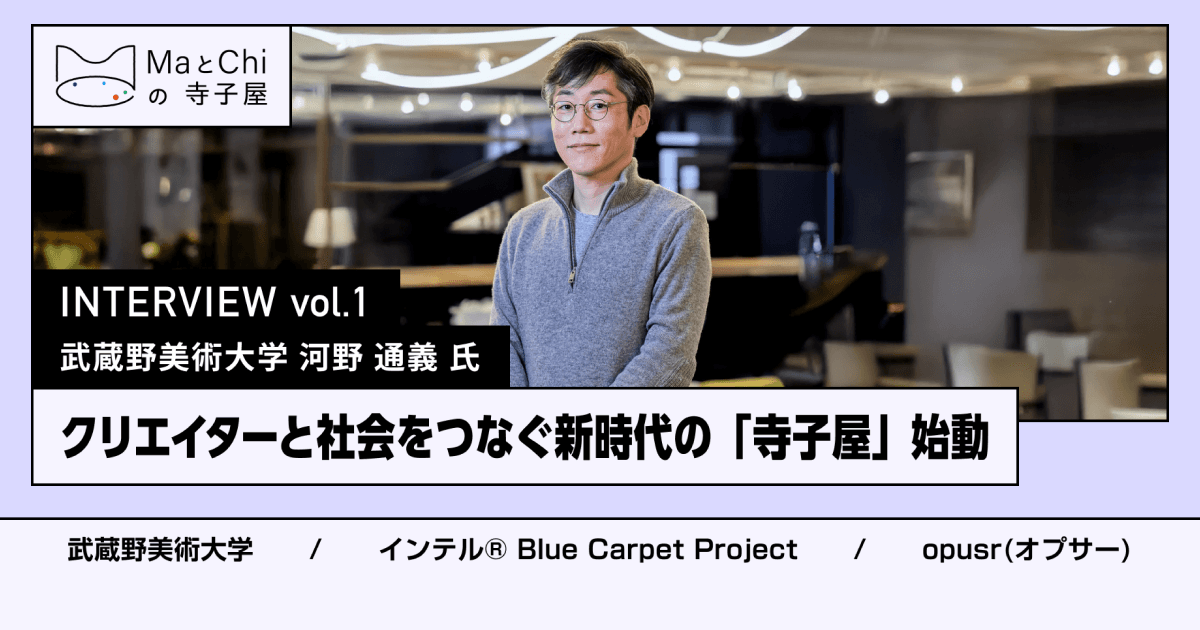
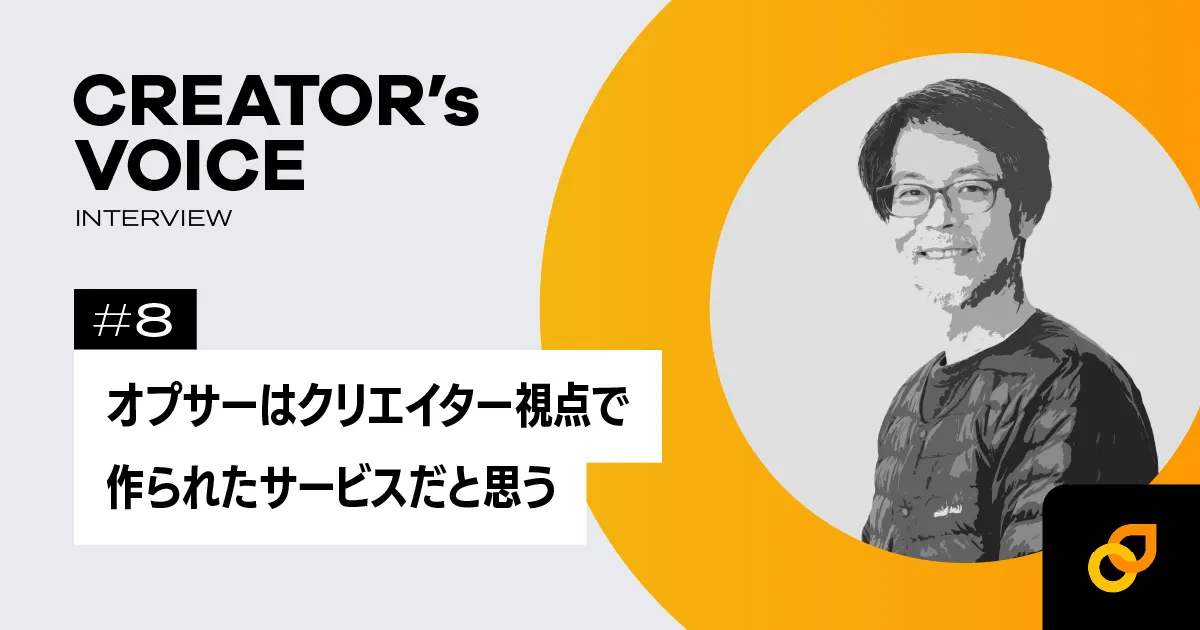
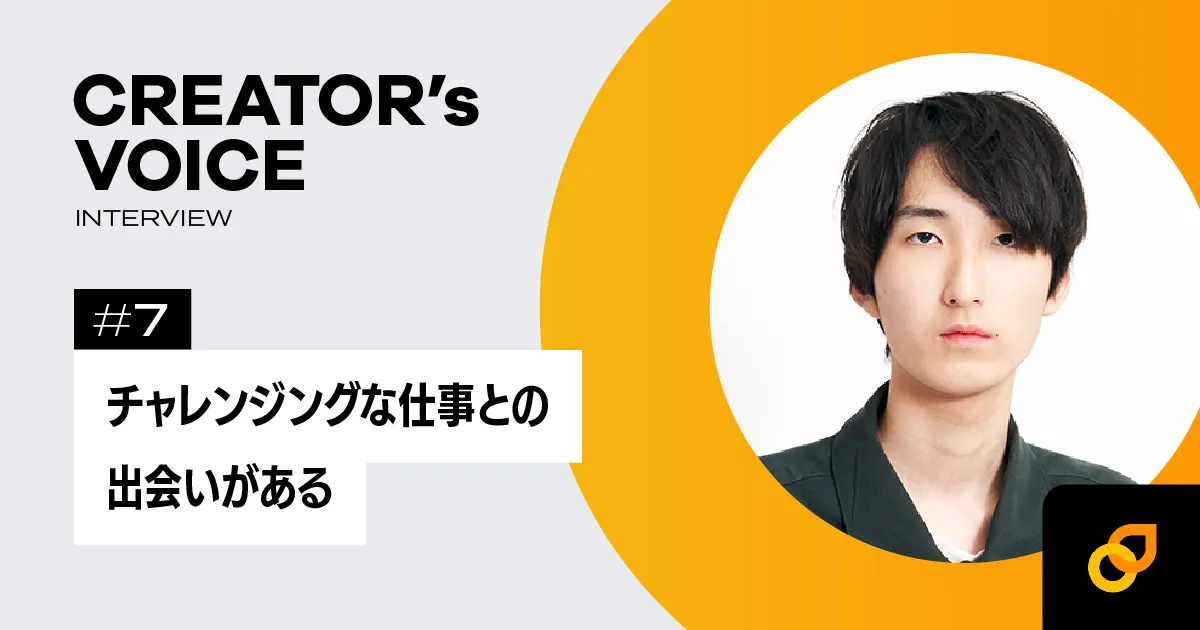
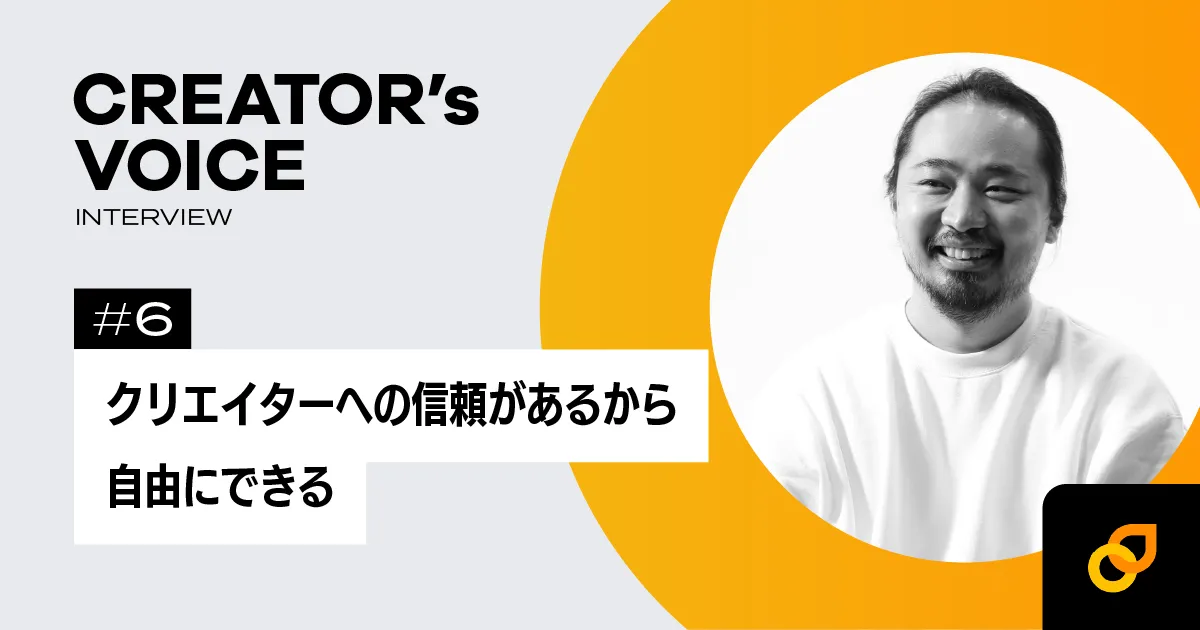
.jpg&w=3840&q=75)