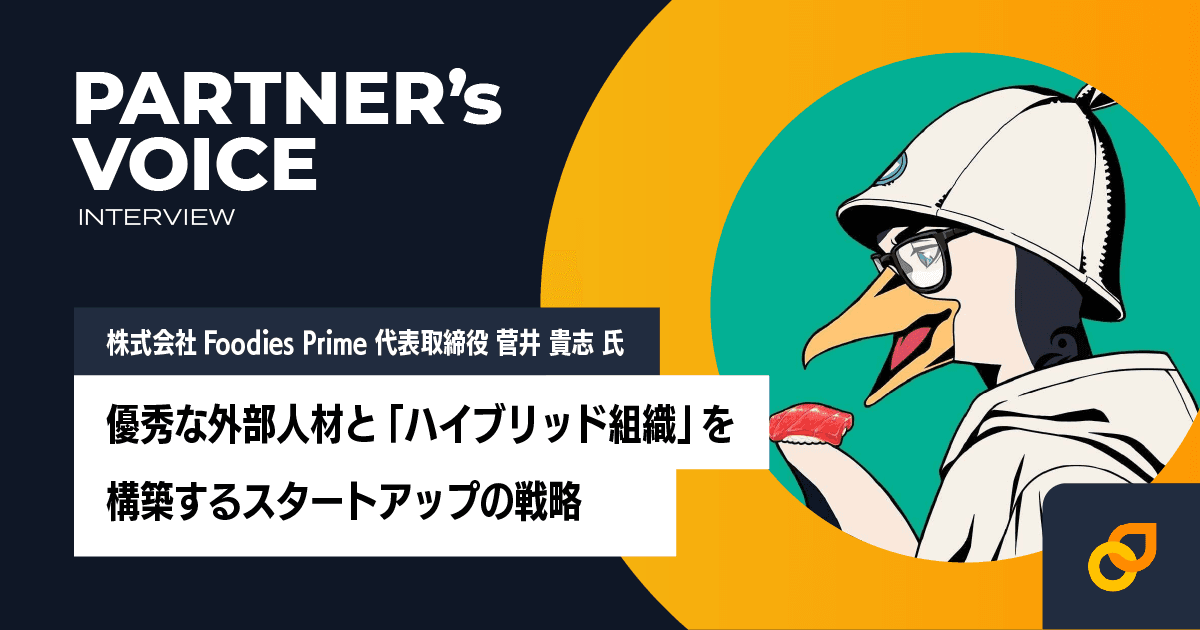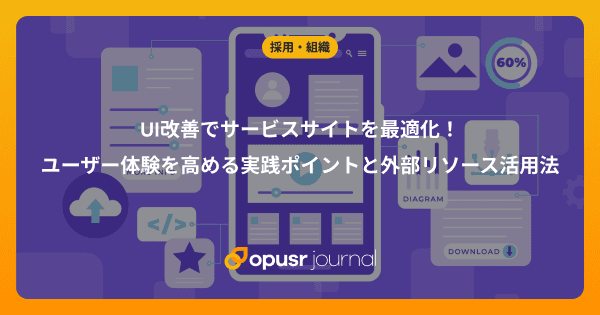イベントレポート<MaとChiの寺子屋 vol.5> 「味ぽん」フォント開発の裏側に迫る|Mizkan・モリサワ・linenが語る「アウトプットの完成度と細部へのこだわり」
山田英子、市川秀樹、岸本真菜都、新藤麻実、河野道義、多湖大師
2026年1月30日(金)、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスの共創スペース「Co-Creation Space Ma」にて、クリエイティブやデザインに関わる人々が集うトーク&ネットワーキングイベント「MaとChiの寺子屋」の第5回が開催されました。
本レポートでは、株式会社Mizkan、株式会社モリサワ、linen株式会社からの3社から4名のゲストをお迎えして行われたセッション「Mizkan・モリサワ・linenと紐解く『アウトプットの完成度の高め方』」の模様をお届けします。
国民的調味料「味ぽん」の60周年のタイミングで制作された「味ぽんフォント」の開発秘話を軸に、ブランド担当者、タイプデザイナー、グラフィックデザイナーそれぞれの視点から、プロフェッショナルたちが追求する「細部へのこだわり」と「完成度の正体」について、多面的な議論が交わされました。
“MaとChiの寺子屋”とは?
「MaとChiの寺子屋」は、クリエイティブやデザインの分野に関わる学生・社会人が、誰でも気軽に参加し、学びあい、交流できる場を提供することを目的として、株式会社ヒューリズムが運営するクリエイターと企業のビジネスマッチングサービス「オプサー」と、武蔵野美術大学が共同主催となって運営するトーク&ネットワーキングイベントです。
スピーカー

山田 英子 氏
株式会社Mizkan / マーケティング本部 マーケティング推進部 デザイン課
2002年入社。営業、経理、総務などを経て2018年よりデザイン課へ。
パッケージデザインのディレクションが主な業務だが、デザイン視点でのブランド強化にも取り組んでいる。「味ぽんフォント」制作の主導や味ぽんのブランドブックのプロジェクトに参加。
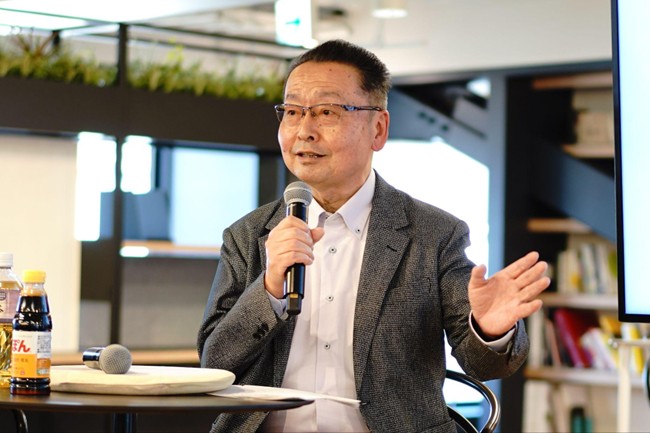
市川 秀樹 氏
株式会社モリサワ / タイプデザイナー
1970年モリサワ文研株式会社に入社。写真植字機文字盤の制作からキャリアをスタートし、勤続56年。「UD新ゴ」ファミリーや「A1ゴシック」など数多くの書体開発に携わる。現在は主に仮名や記号のデザインを担当する熟練の職人。

岸本 真菜都 氏
株式会社モリサワ / フォント営業
2020年入社。Mizkan「味ぽんフォント」開発などのオリジナルフォント案件において、クライアントと制作現場をつなぐ架け橋として活躍。

新藤 麻実 氏
linen株式会社 / 代表取締役・アートディレクター・グラフィックデザイナー
化粧品メーカーのインハウスデザイナーを経て独立。
ブランディングからパッケージ、プロモーションまで一貫したデザインを手掛ける。今回はクリエイターの視点からコメンテーターとして参加。
「味ぽん」60年の歴史と、フォント開発への挑戦
セッションの冒頭、Mizkanの山田氏より「味ぽん」というブランドの歩みと、なぜ今「フォント」を作ることになったのか、その背景が語られました。
まず会場を驚かせたのは、山田氏の異色の経歴です。2002年に入社後、業務用営業、経理、工場の総務などを経て、2018年に現在のデザイン課へ配属されました。美大出身ではなく、ビジネスの現場を渡り歩いてきた山田氏だからこそ、「デザイン」を単なる装飾ではなく、「経営資源」や「ブランド資産」として捉える独自の視点が培われたと言います。

発売から60年以上が経過した「味ぽん」は、当初の「鍋専用調味料」から、焼き魚や餃子への「かけ訴求」、そして「健康志向」「時短調理」と、常に生活者のインサイトに合わせて変化し続けてきました。 その中で、2004年に行われたロゴのリニューアルには、並々ならぬこだわりが隠されています。
「親しみやすさ」と「王道感」、「品質感」のバランス、小さな白い丸
2004年のリニューアル時、デザイナーが目指したのは「親しみやすさ(愛嬌)」と「王道感(スタンダード)」・「品質感」の両立でした。丸みを帯びた愛らしいフォルムの中に、しっかりとした直線を組み込むことで王道感と品質感を表現しています。
山田氏は、「実は『おいしさがひきたちます』というコピーの前に、小さな白い丸がついているのですが、これを外したもので調査をしたところ、お客様からの評価が下がったそうなんです。たった一つの小さな丸が、お客様にとっての『味ぽんらしさ』を支えていることに気づかされました」と語ります。

このエピソードを受け、グラフィックデザイナーのlinen新藤氏は、デザイナーの視点から「味ぽん」ロゴの資産価値について言及しました。
「実は、私が前職で宣伝に携わっていたスキンケアブランド『サボリーノ』から、『味ぽん』とコラボした商品が偶然にも今月発売となりました。これを見た時に感じたのは、『味ぽん』のロゴが、フェイスマスクという異なる世界観のパッケージの中にあっても、すぐ認識できた、という驚きです。長く積み重ねられてきた『味ぽん』という3文字のロゴは、それ自体が代えがたい価値になっていると改めて感じました。」


なぜ「フォント」が必要だったのか?
しかし、その強力な資産であるロゴも、運用面では課題を抱えていました。
味ぽんのロゴのイメージで別の文字を作っても、企画ごとに印象がバラバラになってしまう、似たようなフォントで名前入りのオリジナルラベルを作ると「味ぽんらしさ」が損なわれてしまう、といった事態も発生していました。
「『味ぽん』のロゴには、長年培われてきた親しみやすさや愛嬌に加え、王道感や品質へのこだわりが込められています。既存のフォントでは代替できないこのオリジナリティこそが資産だと気づき、ブランドを強化し、その世界観を正しく継承していくために、公式フォントの開発を決意しました」と、山田氏はフォント開発の経緯を語りました。
「熱意」と「技術」を営業がつなぐ
Mizkanの相談を受けたのが、株式会社モリサワでした。
ある日、モリサワのお問い合わせページからご連絡をいただき、岸本氏が営業担当として山田氏とのコミュニケーションが始まりました。
「発注者と受注者」を超えたチームビルディング
「山田さんの『味ぽんフォントを作りたい』『単に作るだけでなく、ブランドを強くしたい』『社内にフォントに関するノウハウを蓄積したい』という想いを受け止め、社内のディレクションチームやデザイナーである市川と連携し、その熱意に応えられる体制を構築しました。」と語る岸本氏。

具体的には、岸本氏が山田氏と相談した想いをディレクションチームに伝え、Mizkanの「愛嬌」や「熱意」といった抽象的な感情言語を、制作するデザイナーが的確に理解できる「技術要件」や「プロジェクト設計」へと変換しました。
反対に、フォント特有の用語や検討事項についてや岸本氏がMizkanへの説明を工夫してプロジェクトを進めました。
さらに、当初は「ひらがなのみ」の制作依頼だったところを、「今後ブランドが広がっていく未来」を見据え、漢字(UD新ゴ)との混植提案を行うなど、潜在的なニーズを先回りして提案しました。
「仕事において大切なのは、相手の気持ちになること。Mizkanさんはモリサワにとってお客様ではありますが、同じゴールを目指す『ワンチーム』として、対等な立場で意見を出し合う関係性を築けたことが、プロジェクトの成功要因だったと思います」と、岸本氏は営業職ならではの視点で「完成度」への貢献を語りました。
ロゴをフォントへ翻訳する――職人技が光る0.1mmの調整
続いて、実際にフォント制作を担当したモリサワのタイプデザイナー、市川氏による制作プロセスの解説が行われました。
キャリア56年、文字の歴史と共に歩んできた市川氏にとっても、「ロゴをフォント化する」というオーダーは難題だったといいます。
「ロゴ」と「フォント」の決定的な違い、わかりますか?と、市川氏は会場に問いかけます。
「ロゴというのは、それだけで一つの完成された作品です。一方でフォントは、どんな文字と組み合わせても、文章として成立しなければなりません。ロゴのバランスをそのままフォントにすると、文章を組んだ時に文字の並びに違和感を感じてしまうのです」と、話す市川氏。
市川氏は、「味ぽん」のロゴが持つ独特の太さと安心感にマッチするベースとして「UD新ゴ H(Heavy)」を選定しました。しかし、そのまま当てはめるのではなく、職人ならではの緻密な調整が行われました。
0.1mmに込められた「らしさ」の追求
特に議論が白熱したのが、平仮名の「さ」の跳ね上げの角度でした。
Mizkan側からは「もっと角度を寝かせて、愛嬌を出してほしい」という要望が出ましたが、文字のセオリーとして極端な変形はバランスを崩します。
これに対して、市川氏は、「一箇所を変えるなら、全体のバランスを取るために他の部分もすべて調整しなければならない」と語り、跳ね上げの角度だけでなく、縦線の角度や繋がりの形状まで、コンマ数ミリ単位での調整を繰り返しました。

「ロゴの『味』という漢字の縦線と、フォントの縦線の太さは実は変えています。ロゴの方が太いのですが、フォントでは文章としての読みやすさを保つためにあえて少し細くする『太み調整』を行っています。また、ひらがなのサイズ感も、正方形の文字枠にこだわる事なく、「味」「ぽ」「ん」を一つの合字として設計し、ロゴの堂々とした印象を再現しました」と、市川氏は語ります。
こうして完成した「味ぽんフォント」は、Mizkan社内での活用に留まらず、名刺やLINEスタンプ、さらには「自分だけの味ぽんラベル」を作れるイベントなどで活用され、大きな反響を呼びました。
プロフェッショナルたちが考える「完成度の正体」
セッションの後半では、登壇者4名による、「アウトプットの完成度を高めるために最も重要な要素」について、それぞれの立場から語られました。
デザイナー視点:完成度は「余白」に宿る
グラフィックデザイナーとして数々のブランドを担当する新藤氏は、完成度の正体は、「余白」にある、と話します。

「フォント選びもそうですが、私がデザインをする際、最初に決めるのは『どのくらい余白を取るか』です。文字と文字の間、要素と要素の間。そのバランスが自然であればあるほど、完成度は高くなります。経験を積むことで、その余白に対する解像度が上がっていくのだと感じています」
さらに、新藤氏は、技術や情報の変化が激しい現代におけるクリエイターの在り方についても言及しました。
ブランド視点:一貫性こそが信頼
一方、Mizkan山田氏は、「一貫性」を挙げました。
「パッケージからイメージした味と食べたときの印象が違う、ブランドは親しみやすいのに企画だけ尖りすぎている、といった不一致は完成度を下げます。お客様にとっての『味ぽん』であり続けること、その軸が一貫していることが、ブランドとしての完成度だと考えています」
職人視点:56年の経験が導き出した「情熱」と「観察」
56年間に渡り、文字を作り続けてきた市川氏の言葉は、圧倒的な経験値に基づいた職人の立場から、「自分の名前のように愛でること」だと喝破します。
「私の師匠から言われた言葉があります。『もしこの文字が、あなたの名前に使われる文字だったら、あなたは綺麗に作るでしょう?かっこよく作るでしょう?その思いで、すべての文字を作りなさい』と。情熱を持ち、諦めずに観察し続けること。それが全てです」と、会場を奮わせます。
また、市川氏は自身の半世紀以上のキャリアを振り返り、良い仕事をするための要素として「観察力」「感性」「経験」「情熱」の4つを挙げ、次のように総括しました。
「知識も大切ですが、頭だけでなく体で覚えていく『経験』、そして何より諦めない『情熱』がなければ素晴らしい作品は生まれません。私も入社3年目の1973年当時、辞めたいと思った時期がありましたが、そこで踏みとどまり、情熱を持ち続けたからこそ今があります。本物に触れて感性を磨き、対象を深く観察するデッサン力。そうした積み重ねが、言葉では言い表せない『質』になっていくのだと思います」 静かながらも熱い市川氏の言葉に、会場は大きな拍手で包まれました。
ラップアップ:熱量と熱量の掛け合わせが「質」を生む
セッション終了後、本イベントの共同主催者である武蔵野美術大学の河野道義氏と、オプサー(株式会社ヒューリズム)代表の多湖大師によるラップアップが行われました。

オプサーを運営するヒューリズム代表の多湖は、「今回の完成度の正体は、熱量と熱量の掛け合わせだった」と総括しました。
「Mizkan山田さんのブランドを伝えたいという熱量と、それを技術と経験で形にする市川さんの熱量。その二つがぶつかり合ったからこそ、人の心を動かすフォントが生まれたのだと実感しました」と語りました。

武蔵野美術大学の河野氏は、「全く異なるキャリアからデザイン課へ異動し、そこでプロフェッショナルたちと対等に渡り合う山田さんの姿勢に、組織における人材育成や、クリエイティブが持つ可能性を感じました」と、大学という教育機関の視点からコメントを寄せました。
今後のご案内
今回も、ブランド担当者、技術者、デザイナーという異なる立場のプロフェッショナルが集い、予定時間をオーバーするほどの熱気に包まれた「MaとChiの寺子屋」。
参加者からは「文字、フォントの一つ一つに、これほどの技術と物語があるとは知らなかった」「明日からの仕事に向き合う姿勢が変わった」といった感想が、セッション終了後の交流会の中で寄せられました。
「MaとChiの寺子屋」は、今後もクリエイティビティを磨き、刺激し合える場を提供していきます。次回の開催情報はPeatixイベントページよりご案内しますので、ぜひフォローをお願いいたします。
Peatixをフォローする
本イベントに関わる各種団体の詳細や、その他のご案内については以下をご確認ください。
Co-Creation Space Mahttps://ma.musabi.ac.jp/
この記事をシェアする








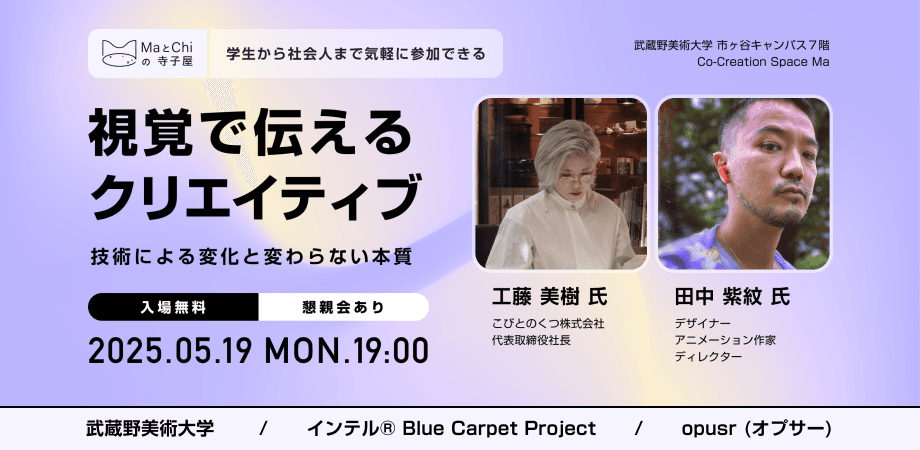






.jpg&w=3840&q=75)